Archive for the ‘未分類’ Category
不正受給詐欺事件で逮捕されたら
不正受給詐欺事件で逮捕されたら
不正受給詐欺事件で逮捕されたらどのようにすべきかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
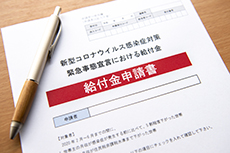
兵庫県丹波篠山市に住んでいるAさんは、市が設置している助成金制度の対象ではないにもかかわらず、助成金の対象であるかのような申請書類を作成し、市に提出しました。
そうしてAさんは助成金の不正受給をしたのですが、後日の調査によって、Aさんの不正受給が発覚。
捜査をしていた兵庫県篠山警察署によって、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、突然Aさんが逮捕されたという連絡を受けてどうすればよいのか分かりません。
そこでAさんの家族は、インターネットの検索で逮捕された人に会いに行ってくれるという弁護士を見つけると、ひとまずその弁護士にAさんの詐欺事件について相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・不正受給による詐欺事件

給付金や助成金、年金等、申請することでお金を受給できる様々な制度が存在しています。
これらの制度を悪用し不正受給をしてしまうと、詐欺罪などの犯罪が成立することが考えられます。
今回のAさんは、受給対象ではないのに受給対象であるかのように偽って申請し、不正受給をしていますが、こういった不正受給のケースにどのように詐欺罪が成立するのか見ていきましょう。
まず、詐欺罪は刑法の以下の条文に規定されている犯罪です。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪が成立するには、以下の流れをたどる必要があります。
①財物を引き渡させるために相手を騙す行為(「欺罔行為」と呼ばれます。)があること
②騙す行為によって相手が騙されること
③騙されたことによって相手が財物を引き渡すこと
これらのどの部分が欠けてしまっても、詐欺罪は成立しません。
例えば、相手が嘘と見抜いた上であえて財物を引き渡したケース(具体的には、詐欺だと気づいたが詐欺をしてでもお金が欲しいのだろうと憐れんで、あえてそのままお金を渡したなど)では、詐欺罪は成立せず、詐欺未遂罪が成立するにとどまると考えられています。
今回のAさんのような不正受給の場合にあてはめてみましょう。
まず、Aさんは助成金の受給対象ではないのに受給対象であるかのように偽って申請をしています(①)。
Aさんから申請を受けた市は、Aさんが受給対象であると騙されていることになります(②)。
そしてAさんが受給対象であると騙された市はAさんに助成金を渡しています(③)。
これによって、Aさんの不正受給行為には詐欺罪が成立すると考えられるのです。
・詐欺罪以外の犯罪も?
 不正受給をしようとする際にその申請に必要な書類を偽造していたような場合には、詐欺罪だけでなく文書偽造罪・同行使罪が成立する可能性も出てきます。
不正受給をしようとする際にその申請に必要な書類を偽造していたような場合には、詐欺罪だけでなく文書偽造罪・同行使罪が成立する可能性も出てきます。
詐欺事件だからといって詐欺罪だけが成立するとは限りません。
複数の犯罪に触れるような場合には、その犯罪同士の関係によって刑罰の重さが変わりますが、詐欺罪のみを犯した場合と比較して厳しい処罰が下されることになる可能性が高いといえます。
弁護活動の内容にも影響が出てくるため、まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談し、成立しうる犯罪がどれほどあるのか、その刑罰としてどういったものが考えられるのか、刑罰の減軽のためにどういった活動が考えられるのか等を細かく聞いてみることがおすすめです。
・逮捕されてしまったら
 家族が逮捕されてしまったら、多くの方は今後どのように対応していけばよいのか、逮捕された家族がどうなってしまうのか、大きな不安を感じられることでしょう。
家族が逮捕されてしまったら、多くの方は今後どのように対応していけばよいのか、逮捕された家族がどうなってしまうのか、大きな不安を感じられることでしょう。
そもそもどういった容疑で逮捕されてしまったのか、逮捕された本人がその容疑を認めているのかどうかも分からないという状況も少なくありません。
上述したように、詐欺事件だからといって詐欺罪だけが成立するとも限りませんし、複数の犯罪が成立する複雑な刑事事件となれば逮捕された本人もその周囲も混乱してしまうリスクがあります。
だからこそ、逮捕の連絡を受けたらまずは弁護士に相談することをおすすめします。
例えば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方に弁護士が直接会いに行く初回接見サービスをご用意しています。
弁護士から直接アドバイスをもらえるため、逮捕されたご本人やそのご家族の不安の軽減に役立ちます。
弁護活動を依頼するにもまずは弁護士と話してみたい、という方にもお気軽にご利用いただけます。
お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けておりますので、遠慮なくお電話ください
ご相談内容別
タクシー乗り逃げで詐欺事件
タクシー乗り逃げで詐欺事件
タクシー乗り逃げ行為で詐欺事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、大阪府高石市にある居酒屋で夜遅くまで酒を飲み、終電を逃してしまいました。
Aさんは、タクシーで大阪府高石市内にある自宅に帰ることにしましたが、タクシーが自宅近くに差し掛かってから、財布にお金がほとんど残っていないことに気づきました。
Aさんは、「どうせ少しの距離しか走っていないのだからいいだろう」と乗り逃げすることを思いつき、運転手に「ちょっと水を飲みたくなったからコンビニで買いたい。一度コンビニに寄ってくれ」とコンビニに寄るように頼みました。
運転手は、Aさんがコンビニで水を購入して戻ってくるのだと思い、言われた通りにコンビニの駐車場にタクシーを停車させ、Aさんが料金を支払わずにいったんタクシーから降りることを許しました。
しかし、Aさんはコンビニに入るふりをしてそのまま逃走し、いわゆる乗り逃げをしてしまいました。
後日、Aさんは乗り逃げの被害届を受けた大阪府高石警察署に詐欺罪の容疑で逮捕されてしまい、困ったAさんの妻は、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・詐欺罪
詐欺罪の規定は、刑法第246条にあります。
刑法第246条
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪には、人をだまして①財物を交付させた場合に成立するもの(いわゆる「1項詐欺」)と②財産上不法の利益を得たり、人に利益を得させたりした場合に成立するもの(いわゆる「2項詐欺」)があります。
詐欺罪が成立するためのざっくりとした要件としては、①人をだまして金銭や物を受け取る、又は、②人をだまして利益を得たり損害を発生させたりすることが必要になります。
このとき、「だます」という行為は単に嘘をつくというだけでは足りず、財物の交付や利益を受けることに向けられ、かつ財物の交付や利益を与える際の判断をする際に重要な事実を偽ることである必要があります。
つまり、「この事実が嘘なら財物を渡さなかった/利益を与えなかった」というような嘘をついていることが必要なのです。
今回の事例について考えてみましょう。
Aさんは、本当は乗り逃げをするつもりなのに、タクシーの運転手に「水を買いたいからコンビニに行ってほしい」という嘘をついています。
タクシーの運転手としては、水を買うためにAさんがタクシーを降りるのだ=この後戻ってきて料金を支払う意思があるのだと信じたからこそ、Aさんが料金を支払わずにタクシーを降りることを許した=タクシーの料金を支払うことをいったん免除していることになります。
当然このAさんの言葉が嘘であると知っていれば、タクシーの運転手は料金を支払わずにAさんがタクシーから離れることを許さないでしょう。
Aさんはこういった嘘をついてタクシー料金の支払いを免れている、つまり、財産上不法の利益を得ていることになりますから、詐欺罪のうち、いわゆる2項詐欺が成立することになると考えられるのです。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役と定められており、裁判になって有罪になり執行猶予がつかなければ、すぐに刑務所へ行くことになってしまいます。
刑務所へ行くことを回避するためにも、詐欺罪で逮捕された場合、早期に弁護士に弁護活動を開始してもらうことが重要です。
タクシーの乗り逃げくらいで、と思う方もいるかもしれませんが、詐欺罪は非常に重い犯罪であり、乗り逃げの態様によってはその詐欺罪に問われることも十分考えられるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、タクシーの乗り逃げによって詐欺罪に問われた場合のご相談・ご依頼も受け付けております。
まずはお気軽に0120-631-881までお問い合わせください。
架空発注詐欺事件で逮捕されたら
架空発注詐欺事件で逮捕されたら
架空発注詐欺事件で逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、大阪市中央区にある会社Vに勤務する会社員です。
ある日Aさんは、実際には存在しない会社に業務を発注をしたように見せかけ、架空の会社に支払う費用として300万円を会社Vから受け取りました。
しかし後日、会社Vの調査によってAさんが申告していた発注が偽物であり存在しなかったことや、その発注費用としてAさんが会社Vから受け取った300万円はAさんが遊興費として使用していたことが発覚。
会社Vは大阪府東警察署に被害申告し、Aさんは大阪府東警察署に詐欺事件の被疑者として逮捕されてしまいました。
Aさんから逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、ひとまず事情を把握したいと考え、弁護士にAさんの下へ接見に行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・架空発注詐欺事件
今回のAさんの事例では、Aさんが架空の発注に見せかけて会社から発注費用としてお金を騙し取っています。
こうした手口でお金を騙し取ることは、刑法の詐欺罪にあたると考えられます。
刑法第246条第1項(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させ」ることが成立の条件とされています。
この「人を欺」くという行為は欺罔行為と呼ばれ、簡単に言えば人を騙す行為を指します。
ただし、ただ嘘をついて相手を騙せば詐欺罪の欺罔行為に当たるわけではありません。
詐欺罪の欺罔行為は、相手が財物を交付するかどうかを判断する際に重要な事項を偽るものであり、かつ財物を交付させるためのものである必要があります。
大まかにいえば、「この事実が嘘であったなら財物の交付はしなかっただろう」という事実について嘘をついて相手を騙すことと、その嘘が相手に財物を引き渡させるための嘘でなければ詐欺罪の欺罔行為とは言えないということです。
そして、「財物を交付させ」るとは、文字通り、財物を引き渡させるということです。
欺罔行為によって相手を騙し、相手が騙されたことによる勘違い等によってお金や物といった財物を引き渡すことで詐欺罪が成立するのです。
今回のAさんの事例のような架空発注詐欺事件についてあてはめてみましょう。
Aさんは、実際にはない架空の発注の費用として会社Vにお金を請求し、お金をもらっています。
このとき、Aさんは会社Vに対して「発注をしたから費用が必要だ」という嘘をついていることになります。
会社Vからしてみれば、正式な発注費用でないのであれば会社のお金を渡す理由はないわけですから、この嘘は会社VがAさんにお金を渡すかどうか判断するための重要な事実を偽る嘘であると考えられます。
さらに、Aさんの架空発注の嘘は会社Vからお金をもらうための嘘ですから、財物の交付に向けられた嘘であるとも考えられます。
こうしたことから、Aさんは詐欺罪の欺罔行為にあたる行為をし、それによって会社Vを騙し、会社Vからお金をもらった=財物の交付を受けたと考えられ、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられるのです。
・会社のお金をとったのに詐欺事件?
ここで、「会社のお金を自分の懐に入れたのだから業務上横領罪になるのではないか?」という疑問を持たれる方がいらっしゃるかもしれません。
刑法第253条(業務上横領罪)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
簡単に説明すると、業務上横領罪は「業務上」=業務として委託を受けて他人の物を管理する上で、その預かっていた他人の物を「横領」=委託されていた権限を越えて自分の物にする等したことで成立する犯罪です。
つまり、業務上横領罪となるには、他人の物を管理する権限を委託されていなければならず、さらにその他人の物を自分の物にする等の行為が必要となります。
例えば、会社で経理を任されていた人が会社のお金を自分の物にしてしまったような場合、その人は会社のお金を経理という立場で管理する権限を会社から与えられていますが、それはあくまで仕事として会社のお金を管理するという内容のものであり、会社のお金を好き勝手してよいということではないでしょう。
そうした権限を越えて会社のお金(他人のお金)を自分の物にしてしまうことになりますから、業務上横領罪が成立すると考えられるわけです。
今回の架空発注詐欺事件のような手口である場合、Aさんには会社のお金を管理する権限は与えられていません。
あくまでAさんは会社Vを騙すことを手段としてお金を手に入れたのであって、自分の管理していた会社Vのお金をとったということではないため、業務上横領罪の構成要件には当てはまらないということになるのです。
架空発注詐欺事件では、架空発注に見せかけるために実際にある会社名義で勝手に偽の発注書を作成するなど詐欺罪の他に文書偽造罪といった犯罪が成立する複雑なケースもあります。
どういった犯罪が成立しうるのか、どのような対応が必要になってくるのかは、それぞれの刑事事件の細かな事情によって変わってきますから、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士がご相談から弁護活動まで一貫してサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
詐欺事件の自白
詐欺事件の自白
詐欺事件の自白について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、千葉市稲毛区に住んでいるVさんに対して詐欺事件を起こしたとして、千葉県千葉北警察署に詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんにはその詐欺事件についての心当たりは全くなく、詐欺事件との関連を否定し続けていました。
しかし、長い取調べが続き、ついにAさんは帰りたいという一心で自分が詐欺事件を起こしたと認めてしまいたいと考えるようになりました。
Aさんの状況を心配した家族は刑事事件に強い弁護士に相談し、弁護士にAさんのもとへ会いに行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・自白
自白とは、犯罪事実の全部又は主要部分を認める被疑者・被告人の供述のことをいいます。
自白については制限が定められており、脅迫や不当な長期間の拘束によって任意にされたものでない疑いのある自白は、証拠とすることはできません。
また、自白が唯一の証拠である場合は、有罪とすることができません。
刑事訴訟法第319条
第1項 強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
第2項 被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
第3項 前二項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。
これは、圧力をかけて無理矢理自白させられてしまったという場合の自白も認めてしまえば冤罪を生むことに繋がってしまうことから、冤罪防止のために作られた規定です。
この規定は憲法に定められている、いわゆる「自白法則」や「補強法則」といったものに基づくものです。
さらに、被疑者・被告人には黙秘権という権利も憲法で保障されていますから、取調べ等で自身の言いたくないことを無理に言う必要もありません。
憲法第38条
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
こうした権利の保障があることから、たとえ圧力や誘導によって自白させられたとしても、任意性がなければその自白を供述調書として証拠とすることはできないものと考えられます。
しかし、実務上、一度容疑を認めた調書が作成されてしまった場合、その供述を覆すことは至難の業です。
というのも、単純に被疑者・被告人が「あの自白は本意ではなかった」と言えば認められるものではなく、自白をした当時の事情や経緯などの客観的な事情も考慮に入れられて判断されるため、「後から自白を撤回すれば済む」という話でもないのです。
だからこそ、本意ではない自白をしてしまった際にはその旨を主張していくことも重要ですが、まずは本意ではない自白を防ぐというところから注力していくことが大切なのです。
そのためには、刑事事件の専門知識のある弁護士から細かい部分までサポートをしてもらうことが効果的です。
例えば、弁護士に弁護活動を依頼すると、弁護士に定期的に接見に来てもらうことができます。
その中で取調べの進捗を共有し合い、次回以降の取調べへの対応の仕方や注意すべきポイントを弁護士に聞いてから取調べに臨むことができます。
不安や疑問を軽減した状態で取調べに対応することで、本意でない自白をするリスクを下げることが期待できます。
さらに、逮捕・勾留されているような事件では、弁護士に釈放を求める活動を行ってもらい、その活動が功を奏し釈放が認められれば、より余裕のある状態で刑事手続きに臨むことも期待できるでしょう。
専門家のサポートを細かく受けられるという環境を作ることで、圧力や誘導によって自白してしまう危険性を少なくすることができるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が詐欺事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
自白についてお悩みの方、詐欺事件について不安な方は、まずは遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
詐欺事件の出頭の前に
詐欺事件の出頭の前に
詐欺事件の出頭の前にするべきことについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、知人Xさんから「簡単に稼げるアルバイトがある」と言われ、Xさんの指示に従い、埼玉県和光市にあるVさん宅に行きました。
そこでAさんはVさんから荷物を受け取ると、Xさんの指示にあった場所に行き、そこで待っていたYさんに荷物を手渡しました。
Aさんは、「これは特殊詐欺などの犯罪に加担しているのではないか」と思いながらも、「ばれなければ大丈夫」と考え、同様のことを複数回行っていました。
しかしある日、Aさんは報道によって、埼玉県朝霞警察署が特殊詐欺事件の捜査をしていることを知りました。
Aさんは、「自分のかかわった特殊詐欺事件が捜査されている。このままでは自分が逮捕されてしまう」と思い、自ら警察署に出頭することを考え始めました。
ですが、警察署に出頭するにしてもその後のことが心配になったAさんは、刑事事件を取り扱っている弁護士に出頭について相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・詐欺事件で出頭する前に
今回のAさんのように、報道などを見て「自分が詐欺事件に関わってしまったかもしれない」と思い、自ら警察署等に出頭したいと考える方は少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも、そのようなご相談は度々寄せられます。
一般の方からすれば、出頭したとしてその後どういった手続きで刑事事件が進んでいくのか、自分がどういった処分や扱いを受ける可能性があるのか、どのように対応していくべきなのか、といった不安は多いことでしょう。
刑事事件に当事者として関わったことがなければ、これらの疑問・不安を抱くことは当然でしょう。
だからこそ、出頭前に専門家である弁護士に相談することが望ましいのです。
では、弁護士に相談することで、どういったアドバイスが受けられるのでしょうか。
まず、詐欺事件などで出頭しようという多くの方が不安に思われることの1つとして、逮捕されるのかどうかということが挙げられます。
自ら出頭するということは、自分から捜査される意志があるということですから、逃げたり証拠隠滅をしたりする意志がないということを示すことができます。
逮捕は逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合になされる手続きですから、自ら出頭することで逮捕のリスクを下げることに繋がります。
ただし、自ら出頭したからといって必ずしも逮捕を回避できるというわけではありません。
今回のAさんの関わった詐欺事件のように共犯者が複数人いるようなケースや、一度逃亡を図ってから出頭したようなケース、余罪が複数件に渡ったり被害額が多いケースなどでは、たとえ自ら出頭しても逮捕されてしまう可能性があります。
ですから、事前に弁護士に相談・依頼することで、まずは逮捕を回避できるよう身元引受人や逮捕によって被る損害の主張を準備したり、逮捕されてしまったとしてもすぐに釈放を求める弁護活動を開始できるように準備しておくことができます。
これは出頭するご本人だけでなく、そのご家族も同様です。
出頭するご本人がたどる可能性のある刑事事件の手続や、その時々にすべき弁護活動をあらかじめ把握しておくことで、ご家族も出頭する方をサポートしやすくなりますし、刑事事件の手続が進む際にも過大な不安を感じずに済みます。
加えて、出頭した後の取調べへの対応も心配されることの多い事柄の1つでしょう。
取調べは、逮捕されていても逮捕されていなくても、被疑者が1人で対応しなければなりません。
警察官や検事といった取調べのプロを相手に1人で対応しなければなりませんから、自分の主張をきちんと伝えられるよう、被疑者の権利を把握しながら話すことが大切です。
しかし、被疑者の権利や取調べへの対応方法などは、なかなか一般の方が知っていることではありません。
弁護士からこうしたことを事前に聞いておくことで、不安を軽減して取調べに臨むことが期待できます。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談を行っています。
詐欺事件に関わってしまった・関わってしまったかもしれないと出頭をお考えの方は、まずはお気軽に、弊所弁護士までご相談ください。
お問い合わせは0120-631-881で受け付けていますので、ご遠慮なくお電話ください。
架空請求詐欺事件で弁護士接見
架空請求詐欺事件で弁護士接見
架空請求詐欺事件で弁護士接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、横浜市中区に住んでいるVさんに、「Xというサイトの無料登録期間が過ぎています。お客様のご登録が継続されているため、利用料金が発生していますが、お支払いを確認できていません。記載の連絡先に至急ご連絡ください。ご連絡がない場合、身辺調査を行った上で、ご自宅やお勤め先に回収にうかがいます」といった内容のメールを送りました。
Vさんは心当たりがなかったものの、記載された連絡先に連絡すると、Aさんから「Vさんがサイトに登録されていることは間違いない。料金を支払ってもらわなければ裁判をして料金を回収することになる。裁判を避けるとなると裁判の取下げ費用もかかることになる」などと言われたため、VさんはAさんに要求された金額を振込み、支払いました。
しかし後日、Vさんが「これは架空請求詐欺だったのではないか」と思い当たり、神奈川県加賀町警察署に相談。
捜査の結果、Aさんは神奈川県加賀町警察署に詐欺罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、まさかAさんが詐欺事件を起こすとは夢にも思わず、急いで弁護士に相談し、詳細な事情を聞いてもらうために弁護士接見を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)
・架空請求詐欺事件
架空請求詐欺は、特殊詐欺の代表的な例である振り込め詐欺の一種とされている詐欺です。
架空請求詐欺の手口としては、手紙やメール、電話などで架空の事実を口実にお金を請求し、指定した銀行口座にお金を振り込ませるといったものが代表的です。
今回のAさんのように、本来登録していないはずのサイトの利用料が支払われていないといった口実でお金を請求し、裁判を起こすことや自宅・勤務先への連絡をちらつかせてお金を騙し取るという手口も架空請求詐欺事件では多い手口と言えるでしょう。
架空請求詐欺は、当然刑法の詐欺罪にあたる行為です。
刑法第246条第1項(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪の「人を欺いて」とは、ただ相手に嘘をつくことを示しているのではありません。
財物を引き渡させるために、相手が財物を引き渡すかどうかの判断をするときに重要な事項を偽ることが詐欺罪の「人を欺」くという条件を満たすと考えられています。
そうして「人を欺い」て、騙された相手が騙されたことに基づいて財物を引き渡すことで詐欺罪が成立するのです。
今回のAさんの架空請求詐欺事件にあてはめて確認してみましょう。
Aさんは、本当はVさんが登録・利用していないサイトの支払う必要のない利用料金をあたかも支払う必要があるようにVさんに請求しています。
Vさんとしては、支払う必要があるものだと言われたからそれを信じて料金を支払ったのですから、最初から支払う必要のない料金だと知っていればお金を振り込むこともしなかったと考えられます。
ですから、Aさんの行為は「人を欺いて財物を交付させた」といえ、詐欺罪が成立すると考えられるのです。
・弁護士の接見
架空請求詐欺事件に限らず、刑事事件で被疑者として逮捕されてしまったらまずは弁護士接見をしてもらうことがおすすめです。
刑事事件で被疑者として逮捕されてしまったら、そこから取調べを受けたり検察庁へ送致されたりといった刑事事件の手続がすぐに始まっていくことになります。
逮捕の伴う刑事事件では、それぞれの手続に時間制限があることから目まぐるしく状況が変わっていくことになりますが、逮捕された際の刑事事件の手続や被疑者の権利、注意しなければいけないポイントなどを全て把握しているという方は少ないでしょう。
だからこそ、早い段階で刑事事件の専門家である弁護士と直接話し、アドバイスをもらっておくことが有効なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方に弁護士が最短即日で接見に向かう初回接見サービスを行っています。
架空請求詐欺事件などで逮捕されてしまった方、逮捕された方が心配だという方は、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。
お問い合わせはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
詐欺事件と窃盗事件で逮捕
詐欺事件と窃盗事件で逮捕
詐欺事件と窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、東京都三鷹市に住む高齢者Vさん宅を訪れました。
そしてX銀行の職員を装うと、「キャッシュカードの切り替えが必要です。切り替えのためには今まで使っていたキャッシュカードを預けてもらい、暗証番号を教えてください」と伝え、Vさんからキャッシュカードを受け取り、暗証番号を教えてもらいました。
そしてAさんは、Vさんから受け取ったキャッシュカードとVさんから聞き取った暗証番号を利用して、X銀行のATMからVさんの預金を引き出しました。
後日、Vさんが見覚えのない引出しに気付いてX銀行に問い合わせを行ったことでAさんの犯行が発覚。
Vさんは警視庁三鷹警察署に被害を届け出て、警視庁三鷹警察署が捜査を開始しました。
その結果、Aさんは詐欺罪と窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは自分のした行為によって詐欺罪が成立することは理解していましたが、窃盗罪まで疑われていることに驚き、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に、なぜ詐欺罪だけでなく窃盗罪も疑われているのか相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・詐欺事件と窃盗事件
今回のAさんは、詐欺罪と窃盗罪の容疑で逮捕されています。
Aさんの行為から、詐欺罪が成立するだろうことは容易に想像できるところでしょう。
刑法第246条第1項(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
簡単に言えば、財物を引き渡させるために相手をだまし、それによってだまされた相手が財物を引き渡すことで詐欺罪が成立します。
そして、このだます行為=「人を欺」く行為は、相手が財物を引き渡す際の判断に重要な事項を偽ることであるといわれています。
つまり、その事実が嘘であるなら財物を引き渡さなかった、と考えられる事実について嘘をつくことが詐欺罪の「人を欺」く行為であるとされているのです。
今回のAさんの事例について考えてみましょう。
AさんはX銀行の職員を装ってキャッシュカードの切り替えが必要であるとVさんに伝えています。
VさんはAさんが本物のX銀行の職員であり、キャッシュカードの切り替えが必要なのであると信じてキャッシュカードを渡しています。
ですから、本当はAさんが偽物のX銀行の職員でありキャッシュカードの切り替えの話が嘘であると知っていれば、キャッシュカードを渡すことはなかったでしょう。
すなわち、AさんがX銀行の職員を装ってキャッシュカードの切り替えが必要であるとVさんに伝えた行為は、詐欺罪の「人を欺」く行為にあたると考えられます。
さらに、今回のVさんはAさんの「人を欺」く行為によってだまされ、キャッシュカードという財物をAさんに引き渡しています。
こうしたことから、Aさんの行為には詐欺罪が成立すると考えられるのです。
ここまでは詐欺罪という犯罪を詳しく知らなくとも予想の付く方が多いのではないでしょうか。
しかし、繰り返しになりますが、今回のAさんにはこの詐欺罪だけでなく窃盗罪の容疑もかけられています。
ここで注意しなければいけないのは、AさんがVさんのキャッシュカードを利用してX銀行のATMから預金を引き出した行為について銀行に対する窃盗罪が成立する可能性があるということです。
刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
今回のAさんの行為はあくまでVさんに対する詐欺事件のように見えますが、なぜ銀行に対する窃盗罪が出てくることになるのでしょうか。
少しずつ確認してみましょう。
まず、ATMなどにある預金は銀行が管理・支配をしているお金です。
通常、その預金を引き出すのは、その銀行に預金をしている預金者本人や、その預金者の同意を得た人であり、その人たちは銀行の管理・支配するお金を引き出す正当な権利に基づいてお金を引き出しているといえるでしょう。
しかし、今回のAさんのケースでは、AさんはVさんからだまし取ったキャッシュカードを用いてVさんの同意のないままに預金を引き出していることになります。
つまり、Aさんは銀行の管理・支配するお金を正当な権利のないまま、銀行の管理・支配するお金を自分の物としてしまっているのです。
窃盗罪は、大まかにいえば他人の管理・支配している物を、管理・支配している人の意思に反して自分の物としてしまう犯罪ですから、Aさんの一連の行為がこの窃盗罪に当てはまる可能性が出てくるというわけなのです。
特に今回のケースのようなキャッシュカードをだまし取る形態の詐欺事件では、このように詐欺罪だけでなく窃盗罪の成立も考えられることが多々あります。
どういった犯罪が成立しうるのか、どれほどの重さとなるのか、弁護士に相談し、今後の活動方針を決定することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件・窃盗事件やその逮捕のご相談も受け付けています。
まずはお気軽に、弊所弁護士までご相談ください。
東京都新宿区の電子計算機使用詐欺事件
東京都新宿区の電子計算機使用詐欺事件
東京都新宿区の電子計算機使用詐欺事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、東京都新宿区に住んでいる会社員です。
ある日、AさんはVさんと食事をした際に盗み見たVさんのクレジットカード情報を利用して、ネットショッピングをしました。
見覚えのないクレジットカードの利用履歴にカードの不正利用を疑ったVさんが警視庁四谷警察署に相談したことで警視庁四谷警察署が捜査を開始。
捜査の結果、Aさんは電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~電子計算機使用詐欺罪~
電子計算機使用詐欺罪は、刑法に定められている詐欺罪の1種です。
刑法第246条の2(電子計算機使用詐欺罪)
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
通常、人を騙して財産あるいは財産上の利益を得た場合、刑法に定められている詐欺罪(刑法第246条)によって処罰されます。
刑法第246条(詐欺罪)
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
しかし、詐欺罪の条文にある通り、詐欺罪は「人を欺いて」財物を交付させる等した場合に成立する犯罪であるため、騙す相手が人ではなくコンピュータ(機械)であった場合は詐欺罪では不可罰とされていました。
それは先ほども触れたように、詐欺罪が成立するにはあくまで「人を欺」くことが要件とされているためです。
例えば今回のAさんの事例では、騙されているのは人ではなくコンピュータ(システム)ということになるため、通常の詐欺罪には当たらないことになります。
さらにコンピュータに他人のクレジットカード情報を与えて買い物をしたというような場合、財物を盗んでいるわけでもないため、窃盗罪(刑法第235条)によって処罰することもできません。
そこで、コンピュータ犯罪への対応を図った昭和62年の刑法一部改正によって新設された犯罪の1つが、今回のAさんの逮捕容疑である電子計算機使用詐欺罪なのです。
電子計算機使用詐欺罪の「電子計算機」とは、いわゆるコンピュータのことを意味します。
そして、電子計算機使用詐欺罪の条文の中に出てくる「電磁的記録」とは、刑法では以下のように定義されています。
刑法第7条の2
この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
つまり、簡単に言えばコンピュータの中にあるデータやシステムのことを指しているのです。
これらのことから、電子計算機使用詐欺罪の成立のために要求される行為は、
①人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産上の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作ること
②財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供すること
以上の2つのいずれかの方法によって、財産上不法の利益を得、または得させることになります。
今回のケースでは、AさんはVさんのクレジットカード情報を無断でVさんの合意なく利用して買い物をしています。
本来こういったクレジットカード情報はクレジットカードの持ち主(今回はVさん)の同意があってVさん本人が入力するものですが、その人の許可なく情報を入力すれば、「許可されていない情報入力」=「虚偽の情報」を与えたことになります。
Aさんはそれによってネットショッピングによって商品を購入していますから、「商品を購入したという内容の情報」=「財産上の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録」ができます。
そして、Aさんはネットショッピングで購入した商品という「財産上不法の利益を得」ているわけですから、今回のAさんの行為は①にあたり、電子計算機使用詐欺罪が成立すると考えられるのです。
電子計算機使用詐欺事件の場合、不正アクセス禁止法違反など詐欺罪以外の犯罪が成立している場合もあるため、刑事事件に強い弁護士に早めに相談・依頼されることをおすすめします。
電子計算機使用詐欺事件やその他の詐欺事件の被疑者となってしまった方、警視庁四谷警察署で取調べを受けることになってしまった方は、お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
振り込め詐欺で組織犯罪処罰法違反
振り込め詐欺で組織犯罪処罰法違反
振り込め詐欺で組織犯罪処罰法違反となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、いわゆる振り込め詐欺を行っている特殊詐欺のグループに属していました。
Aさんは主に受け子と呼ばれる、詐欺の被害者からお金やキャッシュカードなどを受け取る役割をしており、福岡市東区に住むVさんなど複数の被害者からお金やキャッシュカードを受け取っていました。
Vさんが福岡県東警察署に詐欺の被害を届け出たことで捜査が開始され、特殊詐欺グループの存在が明るみに出ると同時にAさんも逮捕されてしまいました。
Aさんは、自分の逮捕容疑が詐欺罪ではなく組織犯罪処罰法違反という犯罪名だったことに驚き、家族の依頼を受けて接見にやってきた弁護士に、組織犯罪処罰法違反とはどういった犯罪なのか聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・特殊詐欺~振り込め詐欺
昨今報道されることも多くご存知の方も多いように、振り込め詐欺は特殊詐欺と呼ばれる詐欺の一種です。
振り込め詐欺などの特殊詐欺事件は、今回のAさんの事例のように、複数人がグループとなって組織的に行われることが多いとされています。
グループの中では詐欺行為の役割分担が決められており、今回のAさんが担当したような被害者から金品を受け取る役割の「受け子」、詐欺の被害者から受け取ったキャッシュカードで被害者の口座から現金を引き出す役割の「出し子」、被害者に詐欺のための電話をかける「かけ子」、詐欺グループの人員をスカウトしたり配置したりする「リクルーター」といった名前で呼ばれます。
こうして組織的に犯行が行われるために振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺事件では共犯者が複数存在するケースが多く、口裏合わせなどの懸念があることから逮捕・勾留といった身体拘束を伴う捜査が行われることも多いです。
さらに、複数の詐欺事件を起こしている場合には、その分再逮捕のリスクも考えられ、身体拘束が長期化するおそれがあります。
・組織犯罪処罰法違反
振り込め詐欺を起こせば当然詐欺罪になる、とイメージしやすいところですが、今回のAさんの逮捕容疑は組織犯罪処罰法違反という罪名です。
詐欺事件を起こしたのに詐欺罪ではないことに疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。
組織犯罪処罰法違反とはどういった犯罪なのでしょうか。
組織犯罪処罰法とは、正式名称「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」という法律で、文字通り組織的に行われた犯罪への処罰を強化し、組織犯罪の防止を行う法律です。
組織犯罪処罰法によれば、刑法上の詐欺罪にあたる犯罪行為を、団体の活動として詐欺罪にあたる行為をするための組織によって行われた場合、1年以上の有期懲役に処するとされています(組織犯罪処罰法3条13号)。
組織犯罪処罰法第3条第1項
次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
第13号 刑法第246条(詐欺)の罪 1年以上の有期懲役
つまり、振込詐欺グループが振り込め詐欺を繰り返しているような場合、まさにこの組織犯罪処罰法違反となってしまう可能性が高いのです。
刑法上の詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですから(刑法第246条)、上限が10年以下と決められておらず、下限が1年以上と決められている組織犯罪処罰法違反の方が重い刑罰が規定されていることが分かります。
執行猶予の獲得や刑の減軽を狙うには、早い段階から示談交渉や再犯防止策の構築などを弁護士と相談して進めていくことが望ましいでしょう。
さらに、先ほど触れたように、振り込め詐欺などによる組織犯罪処罰法違反事件では複数の共犯者が存在するため、逮捕や勾留といった身体拘束がなされる可能性が高いです。
共犯者との連絡を絶つために、接見禁止処分(弁護士以外が面会できない処置)とされる可能性もあります。
ですから、弁護士の接見を通して家族の伝言を伝えたり、様子を把握したりすることも重要であるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間体制でお問い合わせを受け付けております(0120-631-881)。
まずはお気軽にお電話ください。
譲渡目的の口座開設で詐欺事件
譲渡目的の口座開設で詐欺事件
譲渡目的の口座開設で詐欺事件となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、京都市左京区にあるV銀行でAさん名義の預金口座を開設し、通帳やキャッシュカード等を受け取りました。
しかし実は、Aさんは知人であるBさんから頼まれて口座を開設したものであり、Aさんはその口座をBさんに譲渡するために開設しており、自分で利用するつもりは一切ありませんでした。
Aさんは頼まれた通りにキャッシュカードや通帳をBさんに渡して暗証番号などを教え、お礼として5万円をもらいました。
すると後日、Aさんのもとに京都府川端警察署の警察官がやってきて、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
どうやらAさんがBさんに譲渡した口座が特殊詐欺に使われ、そこからAさんにも捜査が及んだということのようです。
Aさんの家族は、Aさん逮捕の知らせを聞いて、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・譲渡目的の口座開設
今回のAさんは、他人に譲渡する目的で銀行口座を開設し、逮捕されてしまっています。
昨今ニュースなどで目にする機会も多い特殊詐欺事件では、捜査の手が特殊詐欺グループにたどり着きにくいようにするため、他人の口座を経由して特殊詐欺グループ本体にお金が流れるようにしていることも多いです。
そのため、多くの口座が必要となり、アルバイト感覚で口座を譲渡させ、その口座を利用して特殊詐欺を働いているというケースも多く見られます。
特殊詐欺を行うことはもちろん詐欺罪に該当します。
しかし、他人への譲渡を目的として自身の口座を作ることも詐欺罪となってしまうのでしょうか。
そもそも金融機関では、口座を他人に譲渡することや、他人がその口座を利用することについては、利用規約などで禁止していることがほとんどです。
上記で例としてあげた特殊詐欺などに利用されてしまうことが考えられますし、銀行にしてみればその人を信用して口座を開設するわけですから、その人本人が利用するのかどうかは大切なことなのです。
ですから、他人に口座を譲渡することを隠して預金口座を開設するということは、銀行からすれば口座を開設するかどうかに関わる重要な事項を偽られているということになるのです。
ここで、詐欺罪の条文を確認してみましょう。
刑法246条(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪の「人を欺いて」というのは、財物を交付する際に交付するかどうかを判断する重要な事柄を偽るということを指します。
先述のように、銀行は他人にその預金口座を譲渡するという目的を知っていれば、預金口座を開設して通帳やキャッシュカード=財物を渡すということはしないでしょう。
ですから、今回のAさんのように、預金口座を他人に譲渡する目的で開設し、通帳やキャッシュカードを受け取るという行為は、銀行に対する詐欺罪に該当すると考えられるのです。
なお、もしもAさんが、譲渡した口座が特殊詐欺に使用されることを知っていたり、そもそも特殊詐欺の計画を一緒に立てて口座を調達する役割を負っていたりするような場合には、銀行に対する詐欺罪だけでなく、特殊詐欺の共犯として、特殊詐欺の被害者に対する詐欺罪についても問われてしまう可能性があります。
・口座を譲渡すると詐欺罪以外の犯罪も
今回のAさんは、譲渡目的で口座を開設していますが、実際に口座を譲渡し、報酬をもらうこともしています。
この行為は、犯収法(正式名称「犯罪による収益の移転防止に関する法律」)に違反する行為になります。
口座を有償で譲渡した場合、犯収法第28条第2項によって1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、もしくはその両方の刑罰を科されることになります。
今回のAさんはそもそも譲渡目的で口座を開設していますが、もともと自分の持っていた口座を有償譲渡したような場合にも犯収法違反という犯罪が成立することにも注意が必要です。
・口座譲渡にかかわる詐欺事件
詐欺事件には被害者が存在しますが、もちろん今回のような口座譲渡にかかわる詐欺事件の場合でも、詐欺行為の被害者が存在します。
ですから、まずは被害者である銀行への被害弁償や謝罪が必要となってくるでしょう。
また、こうした口座譲渡詐欺事件では、特殊詐欺事件の方への関与も疑われ、逮捕や勾留といった身体拘束をともなっての取調べが行われることが予想されます。
組織的詐欺であれば、証拠隠滅のおそれもあると判断され、逮捕・勾留の可能性が高まると同時に、家族であっても面会を禁止される可能性が出てきます。
こうした場合には、取調べへの対応を逐一確認しながらの受け答えや、身柄解放活動や接見禁止の一部解除を目指した活動が重要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、口座譲渡詐欺事件を含む詐欺事件のご相談も多く承っています。
弊所の初回接見サービスでは、お申込みから24時間以内に弁護士が派遣されるため、最短即日での対応も可能です。
口座譲渡詐欺事件の逮捕にお困りの際は、まずは弊所弁護士までご相談ください。





