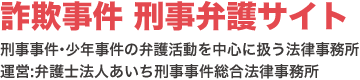(事例紹介)詐欺未遂事件の時効直前に逮捕された事例
~事例~
7年前の詐欺未遂事件で公開手配され、時効まで3か月を切っていた容疑者の男が14日、大阪府警に逮捕されました。
(中略)容疑者は2015年、大阪府枚方市の当時70代の男性に「名義貸しは違法行為です。家族も捕まる」などとウソの電話をかけ、現金600万円をだまし取ろうとした疑いです。
(中略)来年1月5日の時効成立まで3か月を切る中、警察は堺市内のマンションで(中略)容疑者を逮捕したといいます。
(※2022年10月15日12:00YAHOO!JAPANニュース配信記事より引用)
~詐欺事件と時効~
今回取り上げた事例では、詐欺事件の時効直前に容疑者が逮捕されたと報道されています。
今回の記事では、こうした「時効」について注目していきます。
一般に言われる「時効」とは、「公訴時効」のことを指します。
公訴時効とは、その犯罪が終わった時からその期間が経過すると控訴=起訴できなくなるという制度を指します。
起訴できなくなるということは、すなわちその犯罪の容疑で刑事裁判にかけられることがなくなるということですから、その犯罪について有罪判決を受けることもない=その犯罪について罰せられることがなくなるということになります。
刑事ドラマなどで「時効が迫っている」「時効まで逃げ切る」といった表現が出てくることもあると思いますが、これは時効の期間を過ぎれば起訴されなくなる=その犯罪で罰せられることを免れられるということで使われているのです。
では、刑事事件の時効はどのようにして決められているのかというと、刑事訴訟法に詳しく決められています。
刑事訴訟法第250条
第1項 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
第1号 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については30年
第2号 長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪については20年
第3号 前二号に掲げる罪以外の罪については10年
第2項 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
第1号 死刑に当たる罪については25年
第2号 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
第3号 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
第4号 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
第5号 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
第6号 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
第7号 拘留又は科料に当たる罪については1年
刑事訴訟法第250条にある通り、現在日本では、「人を死亡させた罪」のうち、「死刑に当たるもの」についての公訴時効は定められていません。
つまり、人を死亡させた犯罪で、かつ最高刑に死刑が定められている犯罪(例:刑法第199条の殺人罪)については、公訴時効がないということになり、それ以外の犯罪には時効が存在します。
これらの時効の期間が経過すると、公訴を提起できないということになりますが、単にこの期間が経過すればよいというわけではなく、時効の進行にはルールがあります。
刑事訴訟法第253条
第1項 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
第2項 共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。
刑事訴訟法第254条
第1項 時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
第2項 共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。
この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
刑事訴訟法第255条
第1項 犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
このように、状況によっては時効の進行が停止するケースもあります。
すなわち、実質的には時効として定められている期間以上の期間が経過していても、時効としては進行していないというケースがあり得るのです。
時効の期間は、その犯罪の法定刑によって決まります。
今回の事例で問題となっていた詐欺罪について確認してみましょう。
詐欺罪は、刑法で以下のように定められています。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」とされていますから、詐欺罪の刑の長期は「10年の懲役」ということになります。
ですから、詐欺罪は「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪」であり、「長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」です。
そのため、詐欺罪の時効は刑事訴訟法第250条第2項第4号に定められている「7年」ということになります。
報道によると、今回検挙された男性にかけられている詐欺罪の容疑は2015年のものであり、時効は2023年1月とされています。
これだけ見ると、詐欺罪の時効である「7年」を過ぎているように見えますが、先ほど触れた通り、時効の進行は共犯者がいればその最終の犯行が終わった時であったり、時効が停止する場合もあったりするため、こうした事情があって時効が2023年1月となっていたと考えられます。
時効という単語自体はドラマなどでも聞き馴染みがあるかもしれませんが、その仕組みについては案外知らないという方も少なくないのではないでしょうか。
このように、刑事事件の手続では、「聞いたことはあるが詳細は知らない」という制度や権利が存在するでしょう。
そうしたときに頼りになるのは、専門家である弁護士です。
刑事事件への対応にお悩みの際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。